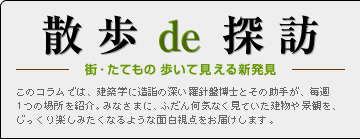※1 江の島の歴史



江の島と対岸の片瀬側とつながっていたおよそ2万年前、沈降運動により島として陸から離れたと推定されている。江の島が干潮時に渡れるようになったのは建保4年(1216)だといわれている。建久元年(1190)北条時政がこの地を参籠した際、龍の化身の女が現れ、子孫繁栄を北条に告げ姿を消した。その場に残された3枚のウロコから、北条家「三鱗」の家紋はつくられたという。慶長5年(1600)徳川家康は下関からの帰路、江の島に立ち寄る。徳川国光こと水戸黄門さまもこの地を参詣に訪れている。また、歌川広重をはじめ多くの浮世絵、風景画に江の島は登場する。相州江ノ嶋岩屋之図(歌川広重)はその代表的作品。
左:歴史が刻み込まれた青銅の鳥居
中:北条家「三鱗」の家紋は江の島の至るところで用いられている
右:エスカーを乗り継いで行けば辺津宮まで一気に登ることができる
※2 江の島弁天橋


江の島に最初に橋が架けられたのは明治24年(1891)のこと。木造の橋は台風のたびに崩壊し流されてしまう。そこで昭和24年(1949)橋桁を鉄筋造りにした大橋が完成する。現在のようなコンクリート建設の橋に生まれ変わったのは昭和33年。6年後の東京オリンピックでヨット競技の会場として江の島が使われることが決定。これに伴い、弁天橋の隣に平行して車専用の江の島大橋が誕生した。
左:参道へと続く江の島の入口
右:片瀬側に向かって延びる弁天橋
※3 サムエル・コッキング苑

この地は古くから金亀山与願寺に所属して、神仏に捧げる供物や食前に用いる野菜を作る供御菜園だった。明治15年(1882)よりイギリス人サムエル・コッキングが神社より買い受け住居と植物園を造った。しかし関東大震災により温室をはじめ家屋のほとんどは倒壊してしまう。昭和24年より藤沢市の整備の末、一般公開されるようになった。2002年4月植物園の改修と展望台の建て替えの際、遺跡の調査が行われた。園内からは縄文時代前期のものと見られる土器や石器など1万点余りが出土した。リニューアルした展望台の高さは海抜119.6メートル。室内から360度のパノラマを楽しめる。旧展望台の台座部をそのまま利用した郷土資料館では、懐かしい展望灯台の巨大ランプや模型に出会うことができる。(サムエル・コッキング苑入場料200円、展望台にエレベーターで上がるとプラス300円)
写真:コッキング苑と新展望台。富士山の眺望がすばらしい。
※4 岩屋



波の浸食によってできた江の島の岩屋は古来より信仰の対象として親しまれてきた。寿永元年(1182)源頼朝をはじめ47人の武士が文覚上人とともに戦勝祈願を行ったことが岩屋に最初に入るきっかけとなったとされている。その後浸食による落石のため閉鎖された時期もあったが、現在では第一、第二岩屋と見学が可能。なお、第二岩屋の先にある龍窟は現在も波の浸食により洞窟が先へと伸び始めている。入場料500円。
左:岩屋へと続く遊歩道。相模湾からの風が心地よい。
中:第一岩屋から第二岩屋へ。そそり立つ一枚岩に圧巻。
右:潮の満ち引きで見え隠れする亀石。竜宮城へ連れて行ってくれる!?